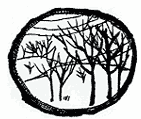| 平成5年の年の瀬もおしせまったある日、机の中を整理していると古ぼけた小さな包みがでてきた。すっかり黄色の変色したそれは、私に北大の学生時代の或る日の一コマを鮮やかに思い出させた。
それは、医学部専門課程へ進学した夏休みのことだった。その頃同じ下宿のT君と、基礎医学のある教室に出入りして研究のまねごとをさせてもらっていた。どちらからともなく、避暑を兼ねて、臨床のほうも研修してみようということとなった。前者の比重が高かったことはいうまでもないが。(札幌でも真夏は30度以上になる日もあり結構暑くなる。むろん、大阪とは比較にならないが)そこで、指導していただいていた先輩にオホーツク沿岸の小さな都市の或る病院の整形外科部長であるK先生を紹介してもらい早速お邪魔することにした。(これがこのあと私の人生に重大な影響をおよぼすことになろうとは夢想だにしなかった)
当地では大学の可愛い(?)後輩ということで歓迎され、3食付きの医師宿舎に泊めていただき、臨床の勉強をさせていただいた。なにしろ、医学生とはいうものの、臨床の経験は皆無であり、(あまり勤勉な学生でもなかったし)とにかく見るもの聞くものすべてが新鮮な驚きの連続だった。
その頃入院していた患者さんにM子ちゃんという可愛らしい女の子がいた。この子は、3歳のときに鉄橋で遊んでいて列車に轢かれ、下腿から切断術をうけたが、骨が成長したため短縮手術をする必要があって入院していた。活発な明るい子で、暇なときに一緒に遊んだりしてなかよくなった。手術は無事にすみ、退院していった。
予定の2週間はまたたくまに過ぎていった。帰る前夜には、K先生に送別会を開いていただき、明け方まで飲み明かした。
翌日、帰る間際になって、K先生が近郊の町の食料品店の名前がかかれた、ちいさな包みを手渡してくれた。それには、”K先生へM子ちゃんより”とかかれていた。両親が、手術のお礼に贈ったものらしかった。ありがたく頂戴して札幌に帰った。
あけてみると、中身は国産の俗に言うダルマというやつであり、貧乏学生のそのころでは考えられない高級ウイスキーであったが、なんとなく飲みそびれたというか、なぜかそんな気持ちになれず結局そのままにしていた。
その後、卒業するまで休暇になると研修と称して、恒例のようにK先生のところにおしかけ、御好意にあまえさせてもらった。
卒業後の専門科目として迷わず整形外科を選んだ。患者を診断から手術を含めて治療まで一貫してみることができることに大きな魅力を感じたのが理由だが、この夏の”研修”体験が大きく影響したことは間違いない。さて、国試にも無事合格し、大阪に帰り、大阪大学整形外科医局に入局してからも、何度か引っ越しする度にいつもこの包みは机の奥深く眠っており、すっかり忘れていた。実に久方ぶりの対面であった。
あれから15年あまりが過ぎていた。10年余りの勤務医生活に別れを告げて、天神の森でグループ診療の一員として整形外科をビル開業してから2年あまりが過ぎたある日のことであった。
この黄色く変色した包みを見て当時のことが鮮やかに脳裏によみがえった。
屈託のない笑顔が可愛かったM子ちゃんは元気でいるだろうか?近年義足は改良されて、テニスができるものまでできている。彼女も脚が不自由なハンデをきっと克服して、成人して幸せになっていることだろう。
私が整形外科医への道を選ぶことに決定的な影響を受けた恩師K先生は、いまは年賀状でしか近況をうかがうことはできないが、その後開業され御盛業とのことである。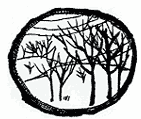
空がどんよりとミルク色に曇り、粉雪が舞い一面流氷におおいつくされた港、それはまさにチャイコフスキーの音楽に描かれるような幻想的な風景はいまも変わりないだろうか。
師走のある日、こんなことを思いつつぼんやりと物思いにふけっていると看護婦の呼ぶ声に我にかえった。
かくして束の間のタイムスリップは終わり、忙しい現実の世界にひきもどされたのであった。 |